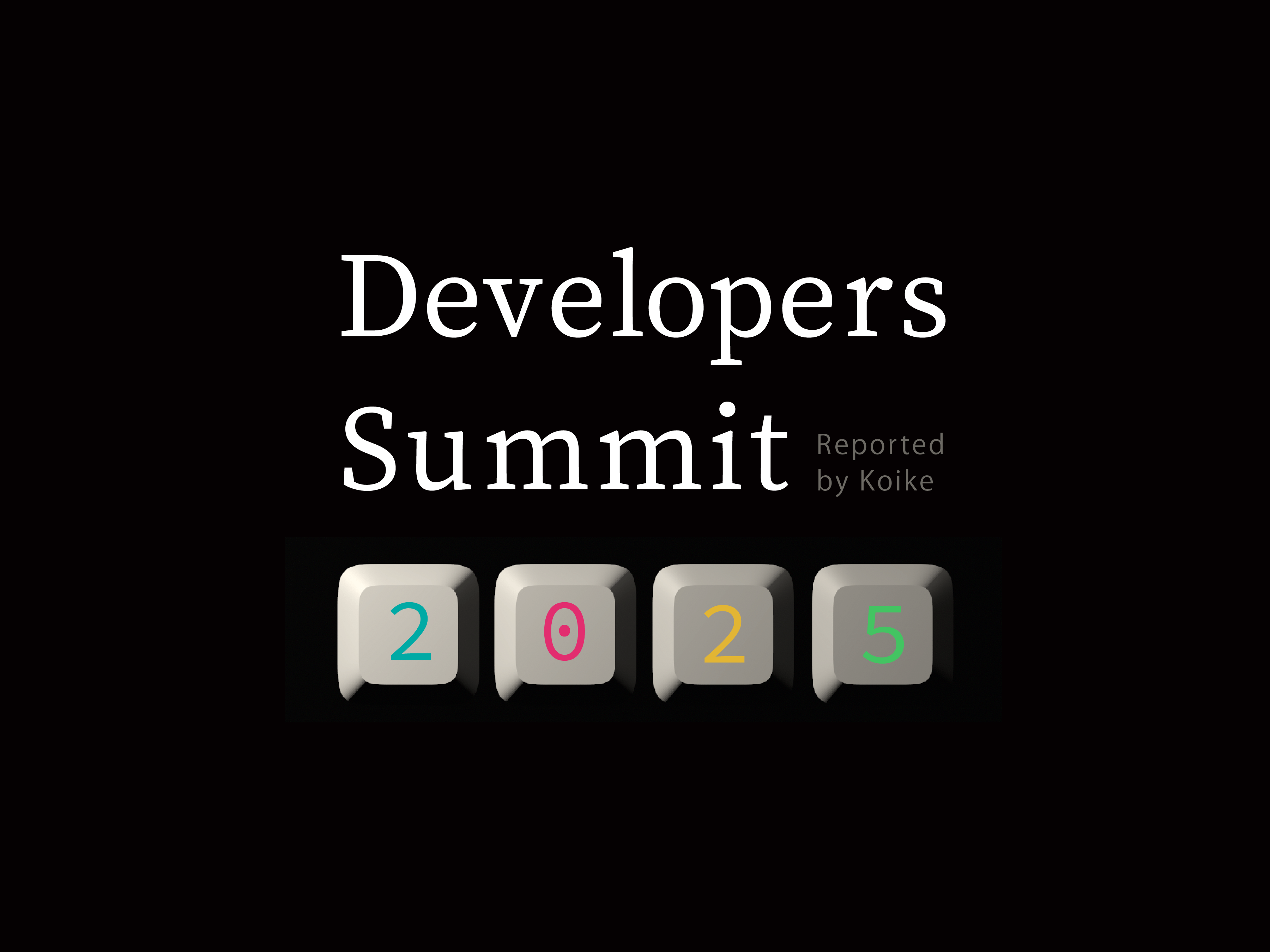
こんにちは、エンジニアの小池です。
今回は2025年2月13日・14日に開催された日本最大級の開発者向けカンファレンス「Developers Summit 2025(通称デブサミ2025)」の参加レポートをお届けします。
品質向上のヒントを求めて
ホテル雅叙園東京で開催されたITエンジニアの祭典「デブサミ2025」。毎年様々なテーマで開催されていますが今回のテーマは 「ひろがるエンジニアリング」です。
エンジニアリングの可能性を広げる技術トレンド、エンジニアの役割の多様さ、エンジニアが越境することで得られるもの、そしてエンジニアリングで社会を大きく変える力について、多くのセッションや企業ブースが展開。
事前の登録では参加者3,000人以上、87のセッションと39社の企業ブースがあり、技術に対する熱量が感じられるイベント会場でした。
私は新たな気づきを得ることを目的に、業務ではなかなか知ることのできない最新技術や、エンジニアリングの考え方に触れるために参加を決めました。
普段から自分自身でも品質向上の難しさを感じており、より良いプロダクトをつくるための取り組みに関心を持っていたため、特に品質向上に関するセッションに注目していました。
今回のレポートではこの話題を中心に、イベントの様子をご紹介したいと思います。

開発品質向上とシフトレフトの重要性
昨今の技術トレンドとして、生成AIやDevOpsが追加されたことで、開発者の負担が増加している風潮があります。
そんな状況でも高品質なシステムであることが求められ、品質の担保は非常に重要な課題になっています。
しかし、品質を担保するためにテスト工数が増大してしまうと、開発作業のリソースがさらに圧迫され、スピーディな開発作業が難しくなります。
今回参加したセッションでは、この問題を解決するアプローチとして「シフトレフト(Shift Left)」 の考え方が強調されていました。
開発フェーズの早い段階からテスト設計・分析を行い、不具合を早期に検出・修正することで、結果的にテストの負担を減らしながら品質を向上させ、全体の工数を抑えるというシフトレフト。この手法は言葉として聞いたことはありましたが、具体的にどのようなものなのか、あまり把握できていませんでした。
今回参加したセッションでは、シフトレフトの「Quality・Speed・Costをマルっと変える戦略と戦術」と題して、欠陥混入の予防と問題の早期発見・解決についての詳しいプレゼンテーションがありました。
欠陥や不備を作らずに開発を進めることが理想ではありますが、人的ミスを完全に防ぐことはできず、不具合のないプログラムを作成することは不可能とも言えます。
そのため、欠陥が作り込まれてしまった後で、検出・除去にかかるリードタイムを最小にすることも重要なポイントであり、後の工程への影響を減らす手立てであることが紹介されていました。
具体的な方法として、以下のような内容を紹介いただきました。
- 実施前に関係者でレビュー観点・テスト観点を共有して作業することで、認識相違によるミスを防ぐ
- 気をつけるべきポイントを上げておくことで、前段階の考慮漏れなどに気づきやすくする
- 作業者がレビュー観点・テスト観点をベースにセルフチェックを実践する
セッション内容を聞いてなるほどと思ったのと同時に、テスト駆動開発などと違い、開発プロセスを大きく変更しないこの方法であれば、私が担当する案件に容易に取り入れることもできそうです。
開発現場での効果の見込みはやってみなければ分かりませんが、ぜひ取り入れていきたいと考えています。
デブサミ2025 今回のまとめ
デブサミは、普段の業務だけでは得られない考え方や技術に触れられる、最新技術や実践的なアプローチについて経験豊富なエキスパートから学ぶことのできる絶好の機会です。
特に、今回知ることができた品質向上のための手法は、実践の場で試していきたいと感じました。
エンジニアとして新たな気づきを得るためにも、次回もぜひ参加したいと思います!
